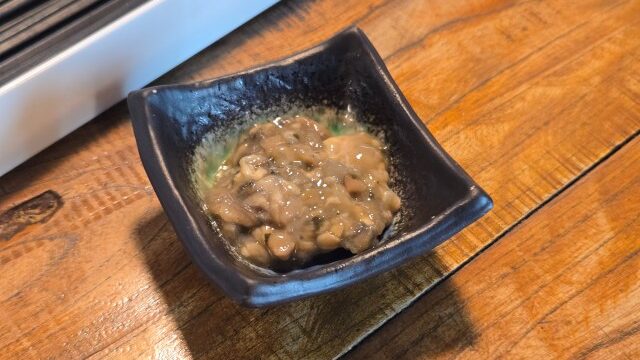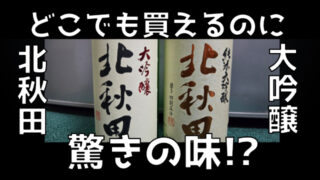お酒はおいしく飲みたいけれど、翌日の二日酔いにはなりたくないですよね。
お酒で失敗してしまう根本的な理由、それは飲んだアルコール量を把握していないからにほかなりません(知らない間に飲んでるんですよね…)
また、自分がどの程度お酒を飲めるのかをきちんと把握していないということもあるでしょう。
この記事では、酔いのメカニズムの紹介も踏まえて、自分が飲めるアルコール量のはかり方と、飲んだアルコール量の把握方法を説明していきます。
これを知ることで、飲む量にブレーキをかけられるようになるかもしれません(おそらく)
また、お酒で失敗したあとでも次に活かせるでしょう。
酔いのメカニズム
飲んだアルコールが肝臓に届くと、
アルコール(有害)→アセトアルデヒド(有害)→酢酸(無害)の2段階に分けて分解されます。
アルコールは脳細胞の働きを低下、いわゆる「酔い」の状態にする物質。アセトアルデヒドは顔を赤くしたり気持ち悪さ(頭痛や吐き気など)の原因を起こす物質。
というように、影響を及ぼす内容が違います。
お酒で気持ちよくなるのはアルコールが分解される前の状態で、頭痛がするようになるのはアセトアルデヒドが分解されずに残ってしまっているからです。(アセトアルデヒドの分解に水分を使いすぎて脱水症状というパターンもあるけど)
お酒の強さも3種類ある
アルコールを分解する能力とアセトアルデヒドを分解する能力はそれぞれ個人差があります。
分解能力を、○=つよい、△=そこそこ、✕=弱いで表すと、以下の分類になります。(横に長くなるので、アルコール = Alc、アセトアルデヒド = AcAld と省略しています)
- Alc○AcAld○ → たくさん飲めるし翌日もケロッとしている
- Alc△AcAld○ → 顔が赤くなりにくく、翌日にも響かないが記憶をなくしやすい
- Alc△AcAld△ → 顔が赤くなりにくく、そこそこ飲めるが翌日に響く
- Alc○AcAld△ → 顔が赤くなりやすく、はやめに気持ち悪くなる
- Alc○AcAld✕ → 顔が赤くなりやすく、すぐ気持ち悪くなる
- Alc△AcAld✕ → 顔は赤くならないのにすぐに酔っ払い、すぐ気持ち悪くなる
となるので、お酒が強いと思われるひとにも、ガチな酒豪、飲めるけど酔いやすいタイプ、翌日に響くタイプの3種類がおります。
みなさんはどのタイプでしょうか?ちなみに僕は、お酒を飲んでも顔に出にくいけど朝まで残るタイプなのでAlc△AcAld△型な気がする。
二日酔いを防ぐ方法
さて、ここから本題です。
二日酔いを防ぐコツとして食事(特にたんぱく質)を一緒に摂るとかお水をちゃんと飲むとかもありますが、根本として、二日酔いになるアルコール量を把握してそれ以上を飲まないようにするという手段をお伝えしたいです。
ただし、アルコール量の限界は個人ごとに違うので、実際に飲んで見極めるしかありません。
適正アルコール量を把握する
現代では、酔いはアルコール量のみに比例するとされています。(日本酒だから酔いやすいというものではない)
お酒の種類を変えてちゃんぽんすると酔いやすいのは、味変をして飽きずに飲めてしまうので知らずにアルコール量が増えていってるだけのようです。
界隈では、アルコール摂取量の基準として純アルコール20gを1単位として考えるとのこと。
(参考)お酒と健康 飲酒の基礎知識(アルコール健康医学協会)
ざっくり言えば、
- ビール(5%)500ml
- 日本酒(15%)1合(180ml)
- ワイン(14%)180ml
- 焼酎(25%)0.6合(108ml)
- ウイスキー(43%)ダブル1杯(60ml)
がどれも1単位(約20gのアルコール量)となります。
ビールは500ml缶があるので把握しやすいですが、焼酎やウイスキーはロックや水割りで飲むので量が把握しづらいですね。カクテルで使うあれを使うしか…。
日本酒やワインは直接グラスに注がず、1合の徳利やデキャンタを経由して飲むことで量を把握しやすくなります。
これで単位ごとに飲んでみて、翌日起きたときの調子を記録していけば、適正アルコール量をおおざっぱに把握することができます。(1合から毎回1単位ずつ増やすのがいいかもしれない)
お酒の量をはかって飲む都合上、アルコール量を把握するときは家で行ったほうがいいかなと思います。
飲み始める時間やペースなども統一したほうがいいとは思いますが、そこはざっくりで。度数も商品によってまちまちですし…。
飲む量を管理する
飲めるアルコール量(または快適に起きられる量)を把握できたら、その量を越えないように飲むようにしましょう。
家で飲む場合は、アルコール量を把握していたとき同様に量をはかりながら飲むと飲み過ぎを防げます。
問題はお店で複数人で飲むとき。なかなか量を把握できないかと思います。
なので個人的には、
- ビール中ジョッキ…0.5
- ビール大ジョッキ…1.0
- ビールグラス…0.3
- ハイボール(チューハイ)薄め…0.5
- ハイボール(チューハイ)濃いめ…0.75
- 日本酒(グラス)…0.5
- 日本酒(徳利)…1.0
- 日本酒(お猪口)…0.2
- ワイン(グラスの半分)…0.5
- ワイン(グラスに波々)…1.0
みたいなアバウトな単位で管理しておいて、グラスの写真を毎回撮影し、一息つくタイミングで写真を見返すのがいいのかなと思います。
失敗したときにも写真を見返して、これだけ飲んだから駄目だったという振り返りをすることで次に繋げることも可能です。写真を撮るのを忘れるくらい飲んでしまった場合は残っている写真の量でラインを引くこともできます。
余談ですが、この方法を取るときにグラスが空いてない状態で追加のお酒を注ぎ足そうとしてくる輩は敵となります。
さいごに
僕の場合、1合ならすっきり起きられる。2合は頭が冴えないけど大丈夫。3,4合だと頭が重い感じ。5合で後悔する。
という風に、1単位ずつ増やしていき、何単位飲んだときに後悔するのか?を見極めるとよいでしょう。
そうしたら、お酒の集まりでもなるべく量を把握して、5単位分は越えないようにペースを調節するとか、度数の低いお酒に切り替えるとかにするとよいでしょう。
自分のアルコール量を把握することは、道路の制限速度を把握することと似ている気がします。限界を理解しているからこそ制限までアクセルを踏めるのではないでしょうか。
なお、飲酒に関わる判断につきましては全て自己責任でお願いします。